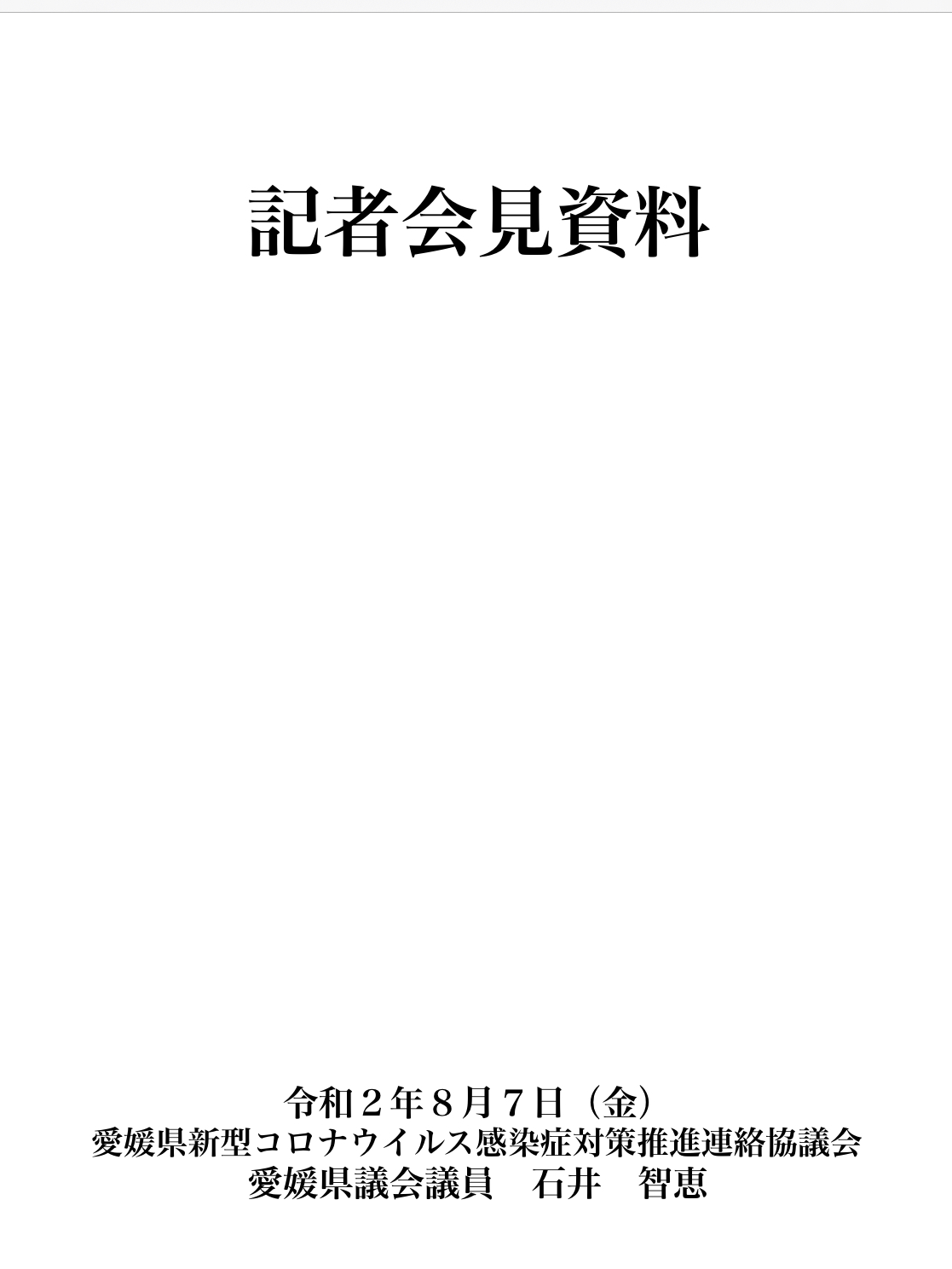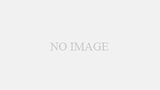【愛媛県新型コロナウィルス感染症対策推進協議会】
【愛媛県新型コロナウィルス感染症対策推進協議会】(記者会見資料)
医療、看護、介護、教育現場のリアルな声を聞き取りしていきました。
(1)医療、看護、介護、教育現場等におけるヒアリング調査について
愛媛県内の実態調査として、各関係機関を対象に非接触型(ズーム、電話等)の聞き取り調査を令和2年6月1日~8月5日の期間で実施した。
以下はヒアリングにて意見の多かった内容を抽出したものである。
◆ 医療関係
( 医療機関全般 )
〇住民のセルフケア意識は浸透してきている。過度な自粛を求める時期ではない。希望する人がスムーズに検査を受けることができ、安心できるようにすることが大切。
〇経営サイドとしては院内から感染者を出すのが怖い、内心ではコロナ患者に手を出したくないと思っている。そのため、感染者が病院から出たら患者が来なくなる、という風潮はなくしてほしい。
〇三密対策の影響により、病床数が3割近く減少に伴う病院経営の悪化による職員への待遇が悪化してしまう。病院スタッフへの還元でモチベーションの低下を防ぐ等、行政に何らかの手立てを講じてほしい。
〇病院間の連携をスムーズにできるように行政には指導してもらいたい。
〇医療現場にも感染者の情報が翌日の15時台にならないと入って来ないため、事前に情報をくれないと濃厚接触者を病院が増やすことになっている。
( 看護 )
〇医療、介護関係者への誹謗中傷、風評被害があっても口に出して言いにくく、黙って我慢しているケースが多い。
〇病院の経営難もあり、ボーナスが減収になった、退職金がなかった人もいる
〇収入が減っても業務は負担が大きく、離職したいと悩む同僚の声を聴く。
〇県の対策について、現場のニーズを十分聞いて対策を講じてほしい。タイムリーに情報共有し、相互に審議できるような仕組みも必要。
〇防護服などは今も不足している。
( 介護 )
〇施設内の感染防止対策を徹底しながら行っているが、外部からの持ち込みによる感染に不安を感じている。
〇感染者が出た時の人員確保について、現在の件の対策がどこまで現実的なものなのか、不明な点も多い。
〇サ高住施設の立場としては、いつ感染された方が転院されるか分からないため不安である。正直、運次第というところもある。〇行政の対応には今更期待していない。
( 救急医療機関 )
〇受け入れた救急車が重なって車内待機が日常化している。車内はプライバシーの都合上解放できないため、救命士・患者・家族が密閉状態になっている。
〇救急車の搬送先分散等、二次救急医療機関における密閉状態を緩和すべく、輪番制の当番に捉われない救急車及びウォークインによる救急患者の受け入れが必要。
〇二次救急医療機関は施設の構造規格に大きな差異があり、救急当番日は外来が満員状態となり、院内ではディスタンスを保つことができていない。
〇救急搬送情報システムを活用すれば患者との接触も減少し、二次感染リスクも抑えられるのではないか。
〇二次救急医療機関の記録を見ると分かるが、患者情報の送信が処置室に入った後に行われるケースが多すぎる。救急搬送情報システムを有効活用できていない。
〇現場の救命士が行うトリアージで搬送しない選択をしやすいようにする。
医師と連絡をとって搬送拒否の決定をすることで責任が分散されるのではないか。
〇救急外来スタッフのなかでも新型コロナウイルス感染症感染疑いの患者に対応できるスタッフは限られる。小さい子供がいるスタッフには対応させられない。
〇新型コロナウイルス感染症感染疑いの患者を対応した後の帰宅に躊躇する。
〇病院における構造上の問題から、発熱や肺炎等の新型コロナウイルス感染症に近似した症状の患者と一般患者を仕切れないため、何時でも救急外来でのパンデミックが発生する状況下にある現実を愛媛県は見たことが有るのか。
〇医療機関外からダイレクトに入れる発熱用の出入り口と待ち合いエリアの確保が必要。
〇救急指定病院間での連携が取れてないので非効率化が進んでいる。病院ごとの棲み分けがあるはずではないか。
〇新型コロナウイルス感染症が蔓延する以前と違い、スタッフは軽微な発熱でも長期の休みを取る必要があるため、深刻なマンパワー不足が幾度となく発生している。休みを取らざるを得ないスタッフへの補助が常時必要な中、救急外来でパンデミック発生のリスクと対峙し続けるのも限界が近いため、現状以上に蔓延する前の対策に期待する。
〇マンパワー不足により業務が煩雑になる。
〇濃厚接触者に該当しているか否かも分からず帰宅している。
〇集中力、サービスの低下による医療事故に繋がるという悪循環が起こり始めている。
〇新型コロナウイルス感染症感染疑いの患者を対応し、採血・CT等の検査後、PCR検査実施病院への紹介状を作成するが、結果はいつになっても分からず、保健所は濃厚接触者に該当しないと言うが、2時間もマスク1枚で患者に付きっきりのスタッフが濃厚接触者に該当しないのであれば一般常識から欠けており、医療機関を甘く見ているとしか考えられない。
医療的観点から見て濃厚接触している救急スタッフをどうケアすれば良いのか困り果てている。陰性なら陰性と教えてくれないと安心してスタッフが子どもと接することができない。市民の命を守るためだけに8日に1日リスクと対峙している。
◆教育関係
( 学校 )
〇新型コロナの感染が国内で広がって以降、全国一斉の休校、慣れないオンライン授業の開始は良いのだが、ハイスペックな機能を全教職員が使い熟し、更に児童生徒に授業をとおして学力向上を促すための実務的な研修等は学校現場で行われていないがやる気なのか。
〇タブレット端末等を配られてから研修を行うなら現実的な導入は来年度からになる。
〇緊急事態宣言解除後に授業時間の延長、夏休みの短縮等により、現場は疲弊している。
〇愛媛県内ではGIGAスクール構想が全国の自治体に比べて整備が遅れている。
( 教育委員会事務局等 )
〇義務教育課程における遠隔授業では、感受性の育成等様々な観点から児童生徒と教職員が相互に顔を合わせる授業が必須であるためICT技術関連の研修を行うことが必要であると考えている。
〇GIGAスクール用端末(ChromeOS)の共同調達には参加していないが、進捗状況を見ると愛媛県は遅すぎる。今後導入したからと言って実用はまだまだ先になる。
〇GIGAスクール構想の推進は「導入と運用」をセットとし、同時進行で考えねば児童生徒の学習は担保できない。
〇自治体内、学校内でのGIGAスクール構想への意識に大きな差がある。